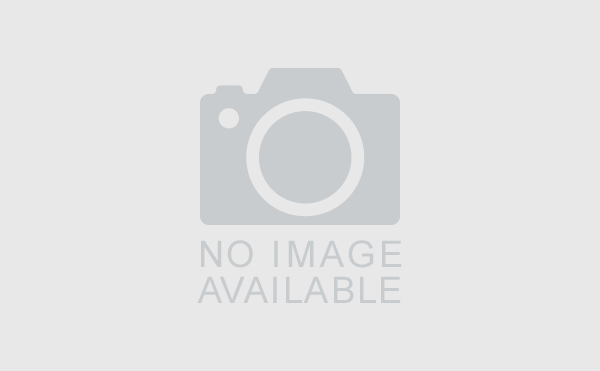2023年12月15日(金)ESD地域研究会(食文化教育フォーラム in 庄内)のご案内および開催報告
日本ESD学会 地域研究会開催報告 「食文化教育フォーラム in 庄内」~ESD/SDGsの視点から考える食文化~
I. 開催趣旨
今世界は、人口増加や気候変動による食糧生産の危機、それに伴う貧困という大きな課題に直面しようとしており、国内では食糧の自給率の低さやフードロスが大きな問題となっている。そのような時、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年の節目の時期で、国立科学博物館においても「和食」特別展が開催されるなど、食への関心が高い。
そこで日本ESD学会は、地域の自然環境を活かした農業を、そして食文化を持続してきた長い歴史を持つ地域の知恵を通して、「食文化」の視点から学校教育におけるESD研究を深めるための研究会を開催した。
会場としては、海の幸や山の幸などの豊かな食材と伝統的な食文化が受け継がれている山形県庄内地方の鶴岡市とした。
鶴岡市には、「行事食・伝統食」が数多く継承され、風土に息づいた精神文化と結びついた食文化が色濃く残っており、農家が数百年にわたり「種」を守り、継いできた「在来作物」が多数確認されている。このように鶴岡は、伝統的な食文化を持つことから、ユネスコ創造都市ネットワークの「食文化」の指定を受けた地域であるとともに、寺子屋時代からはじまった学校給食の発祥の地でもある。
II. 実施要項
日時: 令和5年12月15日(金)13:00~17:30
会場: マリカ市民ホール(山形県鶴岡市末広町3-1) ※オンライン併用
主催: 日本ESD学会 (ESD地域研究会in庄内実行委員会)
※ 日本ESD学会会員
実行委員長 見上 一幸 (※ 学会長)
実行委員
浅野 亮(※ 気仙沼市・宮城教育大学連携センター)
阿部 大輔(※ 山形市立千歳小学校)
市瀬 智紀(※ 宮城教育大学教授)
井上 郡康(※ 東北地方ESD活動支援センター)
小林 拓世(※ 宮城県多賀城高校)
鈴木 泰行(鶴岡市食文化創造都市推進課)
内藤 恵子(※ 仙台ユネスコ協会)
渡邉 智(鶴岡市教育委員会)
共催: 宮城教育大学ESD/ユネスコスクール・東北コンソーシアム
後援: 鶴岡市、鶴岡市教育委員会、鶴岡食文化創造都市推進協議会、酒田ユネスコ協会、仙台ユネスコ協会、山形大学農学部、東北地方ESD活動支援センター、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
III. 発表プログラム
当日の講演、事例発表の動画を鶴岡市により公式YouTubeで公開しており、そのURLを表記する。
I. 基調講演
「在来作物の魅力と課題」
山形大学農学部教授 江頭 宏昌 氏
https://youtu.be/RTGpB_PJ-tg?si=A2_qlGnQVdDCL4Jv
・・・以下に、講演の要点の一部を記録した。・・
1.イントロダクション
鶴岡市行沢(なめさわ)には1000本におよぶ江戸時代に植林されたトチノキ林があり、トチノキは水源涵養、実は保存食、花は蜜源、材はこね鉢などになること、「トチを切る馬鹿、植える馬鹿(環境民俗学者の野本寛一が静岡県で記録した言葉;自分の代には実らず、子孫のための植林)」という言葉があること、実の高濃度のサポニンを除去して食用に変える伝統的な知恵がある。
山形県には多様な在来のカブがある。トチを利用してきたことにも理由があるように、なぜそこにその在来作物があるのか理由があるので、その理由を考えることが大切である。
カブは生育期間が短く蒔いて1ヶ月後には食べられ、低温下でも生育が早い。盆過ぎに種子を播いても降雪前に収穫が可能で、生カブは雪中で1月ころまで保存でき、漬物にすれば3月下旬まで貯蔵が可能なことから飢饉回避の知恵である。難を逃れるために、このような理由から全国に在来のカブがある。
現代は、食べもののありがたさを理解するのが難しく、飢饉に対する現実感がないのでリスク管理が難しい。飢饉の恐ろしさやひもじさを親も知らず、子どもに語ることもできない。かつて私たちの先人は豊かな食に恵まれたいと願い、祈ってきた。少ないときは少ないなりに食べ、多いときは余剰を丁寧に保存して食べた。食べものは、「天の恵み」という感覚はなくなり、いつもふんだんにあるのが当たり前になっている。
日本の食糧事情を考えたとき、日本の食は輸入トウモロコシで支えられていると言っても過言ではない。そして、日本の作物生産の大部分は化学肥料、被覆材、動力機械など「石油」に依存し、流通も「石油」に依存しており、日本のエネルギー自給率は11.8%(2018年)である。
食料を生産するには、まず「種子」が必要である。しかし種子を生産できる人が高齢化で風前の灯火。もし種子の供給がなくなったらどうするか。お金があれば食料が買えるが、他国が売ってくれなくなったら、高騰したら、私たちは暮らしていけるだろうか?
2.在来作物とは何か
在来作物とは、ある地域で、世代を超えて、栽培者によって 種苗の保存が続けられ、特定の用途に供されてきた作物とのことである。
「在来作物」は、1)世代を超えて種苗の保存(自家採種)が続けられていることと、2)世代を超えて栽培・利用されていることの2つの条件を満たす作物であるので、誰でも身の回りの貴重な作物資源への認知を拡げることができる。
近年「伝統野菜」は地域の団体が、野菜のブランド化や地域振興を目的として、特定の条件を付けて認証したものを指すことが多い。
近代品種は圧倒的に生産性が高い。その結果、種子・苗は買ってくるものになった。そして採種しなくなり、国内の伝統的な採種の技術と文化がほとんど消滅してしまった。
作物が換金手段になり、稼ぐために生産性が高い品種、売れる品種が優先的に栽培されるようになり、需要のない在来品種は栽培されなくなった。優秀な商業品種も、遺伝子組換え作物も、ゲノム編集作物も生産性・経済性を合理的に追求してきた社会の価値観を反映したものであり、在来品種の消失を根本的に否定することは困難である。
3.在来作物の魅力と活用
それでも在来品種を継承する意義はどこにあるのか。それは「野菜の在来品種は生きた文化財」だから消滅させてはいけない(青葉高氏)という言葉に集約されるだろう。文化財とはそれが存在することで地域の歴史や文化を伝えることができるメディアだということである。
在来作物は、庄内地方に90種類、うち鶴岡には60種類ある。民田ナス 小真木大根 大滝にんじん 小真木だだちゃ 孟宗 庄内柿 黄金ミョウガ 甲州ブドウなど・・・。
だだちゃ豆は有名であるが、そのルーツを探ると新潟と山形(鶴岡)の人の交流によって、 両県に良食味のエダマメ(茶豆)文化が誕生した。
「持続可能な社会づくり」を支えるのが「多様性」と「つながり」であるが、在来作物にはまさにその魅力が備わっている。また、在来作物を通じて地域の個性(本質)を再発見する手がかりとなるので、地域の魅力を引き出したり、地域外にアピールすることにも役立つ。
在来作物を保存・継承・活用するのに、学校が関わる例がある。酒田市立八幡小学校6年生は、地元農家とともに八幡地区に100年以上前から伝わる升田かぶの栽培に取り組んでいる。
4.在来作物継承のための課題
在来作物の継承に必要なことは、
1) 栽培者にとって、現代の価値観に合いにくい作物を今後も守る意義、支えは何か。
2) どこに、どんな特徴や文化・歴史的背景を持つ在来作物があるのか、どうすればそれを見たり、入手したりできるのかという情報へのアクセス。
3) 自家採種の技術と文化をどのように継承するか
4) 栽培環境の変化(地球温暖化による熱波や干ばつ、豪雨への対策、鳥獣害、受粉してくれるハチの激減、宅地化と家庭菜園による交雑のリスク)に対応した栽培法と採種法の模索が必要。
5) 少量多品目の農産物の需要と供給をつなぐ仕組みが必要。
6) 在来品種を使った郷土食を若い世代が食べる機会や新たな食べ方の開発が必要で、給食の役割も重要である。
II. 実践校の発表
1) 地域とつながる未来へつなげる外内島きゅうり
鶴岡市立斎小学校 三浦皆人 渡會 奏
https://youtu.be/MVUNj4UdSFY?si=WL1URs0z1Gm1z2SS
2) 地域特産品を使った災害食の開発~災害食が世界を救う~
宮城県多賀城高等学校災害科学科
鈴木こころ 真壁結音 髙沢流萌 https://youtu.be/A5fo3NInN7g?si=K58SCrDnuUhgUjzA
3) 新しい藻場造成法の研究
山形県立加茂水産高等学校
3年 海洋資源科 阿部清輝・富樫琉永 https://youtu.be/HIxNVJTjRaM?si=uWwtkuIVr5wmCDkO
4) 小さなタネがつなぐ地域と子どもたち
社会福祉法人 恵泉会鶴 岡市小堅保育園
https://youtu.be/nnnpocdLjOs?si=DFWRZ6xWSqKQaNrd
5) 和食講座~ユネスコスクールとの連携を通して~
白石ユネスコ協会 佐々木隆行
https://youtu.be/EQhBhutAO38?si=KytLZyntFQCKFJuW
6) 気仙沼のスローフードに向き合う「海と生きる探究活動」の取組
気仙沼市立鹿折小学校教諭 内海 千秋
https://youtu.be/SDY2K40C2iw?si=6lw6zKOfvdCA7mHW
7)星めぐりの白菜物語~地域の食文化を活用した食の学び活動と内発的地域振興~
仙台大学附属明成高等学校
https://youtu.be/U6Xmj_kK8BQ?si=COS9qYmnGv9h5cLK
8)臼杵の豊かな食文化を活かした学校教育について
臼杵市教育委員会学校教育 https://youtu.be/VipyDzrSjDg?si=LtA5wwywoDf6x2ZH
Ⅲ.フォーラムディスカッション
テーマ「ESD/SDGsの視点から食文化をどう教育に取り入れるか」
ファシリテータ:
阿部大輔(山形市立千歳小学校)
登壇者
佐藤久哉 (山形県立加茂水産高等学校)
三浦裕美 (鶴岡市食文化創造都市推進課)
地主友昭 (酒田ユネスコ協会)
浅野 亮 (気仙沼市・宮城教育大学連携センター)
内藤惠子(仙台ユネスコ協会)
https://youtu.be/qROI0hZzraw?si=NZ4GBzXvwXGK7YKO
食には地域の個性があること、食の知恵が受け継がれてきたこと、食を通して人を育てるのが食文化であることなどが述べられ、食文化の観点から考えると、「食」を切り口に、生き方を考えるのがESDではないか。本日ここに,色々な地域の方々が集っているので、コミュニケーションをとって,皆で盛り上げ,子どもたちにつないでいきたいという結論に至った。
IV. 講評
日本ESD学会前会長 長友恒人(奈良教育大学 名誉教授)
実践報告は保育園から高校まで、どの実践も理解や調べ学習に終わらない素晴らしい発表内容でした。
「食」に関する取り組みで、地域の皆さんの力を借りて、繋がりを大事にしていることも共通した特長です。地域の人たちの伝統野菜継承の取り組みと結ぶことでローカルの優れたところと課題の両方が見えてきます。児童・生徒の年齢にもよりますが、在来品種が減少してきた背景の学習を深めることによって、日本と世界の食料事情の課題が意識化され、「グローカル」な実践になるでしょう。
伝統野菜のキュウリやなすを収獲するだけでなく、間引きや水遣りなども自分たちで行い、種子を採って次年度に引き渡すまでの実践報告も素晴らしいと感じました。地域の方に教えていただきながらも、野菜作りの種の採取まで全課程を経験することは単なる体験学習を越えた「繋ぐ」学習になっていると思います。
ユネスコ協会がユネスコスクールと協働していることは東北のESDの特長ですが、小規模でもいいので、参加しやすい研究会・実践交流会・情報交換会などを継続して行うことで「やる気」も継続し、実践の質も向上します。東北のESD実践の今後を期待したいと思います。
V. 主催者としての自己評価
本研究会は、鶴岡市のご配慮によりJR鶴岡駅前の会場の提供をいただき、対面とオンラインでの参加で開催した。会場の収容定員100名は満杯となり、オンラインでの参加も北海道旭川から九州大分まで多くの参加をいただいた。
今回の研究会をとおして、ESDを推進の上では、地域にこそ、さまざまな教育的資源があることを改めて確認できた。経済的、社会的、文化的、環境的な側面から創造性を重視する世界的な都市間のネットワークとして、ユネスコ創造都市ネットワーク(the UNESCO Creative Cities Network)がある。「食文化」の分野で指定された都市は、国内では鶴岡市の他に、豊かな食文化の伝統がある大分県臼杵市が認められている。今回、臼杵市からも発表いただくことができ、課題を共有することができた。
さらに今回の研究会を通じて、創造都市ネットワークやユネスコスクールネットワークの他、酒田ユネスコ協会、仙台ユネスコ協会、白石ユネスコ協会、旭川ユネスコ協会など、ユネスコの関係機関との連携も学校教育に有効であることも明らかにすることができた。
ⅤI.謝辞
日本ESD学会は、ユネスコスクールやユネスコ協会、ユネスコ創造都市ネットワークなどUNESCOのネットワークを活かしながら、ESDの質の向上とSDGsの達成に向けて、学校教育を中心とした研究会を鶴岡市で開催することができた。これは鶴岡市の皆川市長のESDへの深い理解と、食文化創造都市推進課の全面的な協力があってこそ開催することができた。鶴岡市のみなさまに深く感謝する。
また、デザインでユネスコ創造都市に指定されている旭川市の林朋子旭川ユネスコ協会会長からも本研究会に励ましのメッセージをいただいたことに感謝する。
また、大分県臼杵市教育委員会との連携については、大分大学教職大学院准教授の河野晋也先生のご尽力のあったことを記すとともに、今回の研究会が地元庄内、鶴岡の絶大なご協力をいただけたことについて、酒田ユネスコ協会の地主友昭会長のご尽力によることもご報告させていただき、感謝したい。
以上、記録者 見上一幸
(以降は過去の情報です。)
下記のとおり、山形県鶴岡市において日本ESD学会のESD地域研究会を開催します。

(ポスターのPDFファイルはこちらからダウンロードできます。)
「食文化教育フォーラム in 庄内 ~ESD/SDGsの視点から考える食文化~」
主催:日本ESD学会 「食文化教育フォーラム in 庄内」実行委員会
共催:宮城教育大学ESD/ユネスコスクール・東北コンソーシアム
後援:鶴岡市教育委員会、鶴岡食文化創造都市推進協議会、酒田ユネスコ協会、仙台ユネスコ協会、山形大学農学部、東北地方ESD活動支援センター、他
【趣旨】
世界の人口増加や気候変動による食糧生産の危機、それに伴う貧困という大きな課題に直面しようとしています。また、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年が過ぎ、国立科学博物館でも「和食」をテーマに特別展(和食展 開催期間 10月28日~来年2月25日まで)が開催予定です。この機会に、地域の自然環境を活かしながら農業を、そして食文化を持続してきた地域の知恵を通して、持続可能な社会を考えたいと思います。
開催地である鶴岡市のある庄内地方は、古くから固有の農作物を栽培し、系統保存を行い、伝統的な食文化を持つことから、ユネスコ創造都市ネットワークの「食文化」の指定を受けた地域であるとともに、寺子屋時代からはじまった学校給食の発祥の地でもあります。
日本ESD学会は、ユネスコのネットワークを活かしながら、ESDの質の向上とSDGsの達成に向けて、学校教育を中心とした研究会を開催します。
【開催日時】令和5年12月15日(金) 13:00~17:30
【会場】 鶴岡市 マリカ市民ホール(〒997-0015山形県鶴岡市末広町3-1)
【対象】 教員、学生、一般市民
【参加申し込み】 追って発表いたします。
※オンラインによる配信も行う予定です。
【参加費】 無料
【プログラム】
12:30 受付
13:00 開会行事
I. 基調講演 13:10~14:10 「鶴岡地域の在来農作物の維持について」(仮)
山形大学農学部教授 江頭宏昌氏
II. 実践校の発表(発表順未定)
(1)14:15~14:30 「内島きゅうりなど在来作物の栽培などに係る実践発表」
鶴岡市立斎小学校 三浦皆人氏・渡曾 奏氏
(2)14:30~14:45 「防災と食教育(仮)」 宮城県多賀城高等学校 (未定)
(3)14:45~15:00 「新しい藻場造成法の研究」
山形県立加茂水産高等学校 阿部清輝氏・富樫琉永氏
(4)15:00~15:15 「小さなタネがつなぐ地域と子どもたち」
鶴岡市 小堅保育園 池田絵里香氏
≪休憩≫
(5)15:25~15:40 「和食講座〜ユネスコスクールとの連携を通して」(仮)
白石ユネスコ協会 佐々木隆行氏
(6)15:40~15:55 『気仙沼のスローフードに向き合う「海と生きる探究活動」の取組』(仮)
気仙沼市立鹿折小学校 教諭 内海千秋氏
(7)15:55~16:10 「星めぐりの白菜物語」
~地域の食文化を活用した食の学び活動と内発的地域振興~(仮)
仙台大学附属明成高校 (未定)
(8)16:10~16:25 臼杵の豊かな食文化を活かした学校教育について(仮)
臼杵市教育委員会 学校教育課 指導主事 玉ノ井智則氏
Ⅲ.フォーラムディスカッション 16:30~17:30
基調講演および発表校の実践を踏まえて、ESD/SDGsの視点から食文化をどう教育に取り入れるかについて総合的に検討する。
【メッセージ(見上一幸)】
ESDの推進の上で地域にはさまざまな教育資源があります。ユネスコ創造都市ネットワーク(UCCN:the UNESCO Creative Cities Network)もその一つで、経済的、社会的、文化的、環境的な側面から、創造性を重視する世界的な都市間のネットワークです。国内では山形県鶴岡市と大分県臼杵市が「食文化」で認定されており、豊かな食文化の伝統があります。本研究会開催地の鶴岡市には、「行事食・伝統食」が数多く継承され、風土に息づいた精神文化と結びついた独自の食文化が色濃く残っており、農家が数百年にわたり「種」を守り継いできた「在来作物」は多数確認されております。また、鶴岡市は学校給食発祥の地でもあります。
このような地域の文化を学校教育に活かすために、日本ESD学会は鶴岡市を会場に12月15日に研究会を開催します。ユネスコのネットワークである創造都市ネットワーク、ユネスコスクールネットワーク、各地のユネスコ協会等のネットワークを、学校教育にどのように活用するかについても考える良い機会になると考えます。鶴岡市のご協力をいただき、会場への参加も、オンラインでの参加も可能ですので、どうぞお気軽にご参加ください。